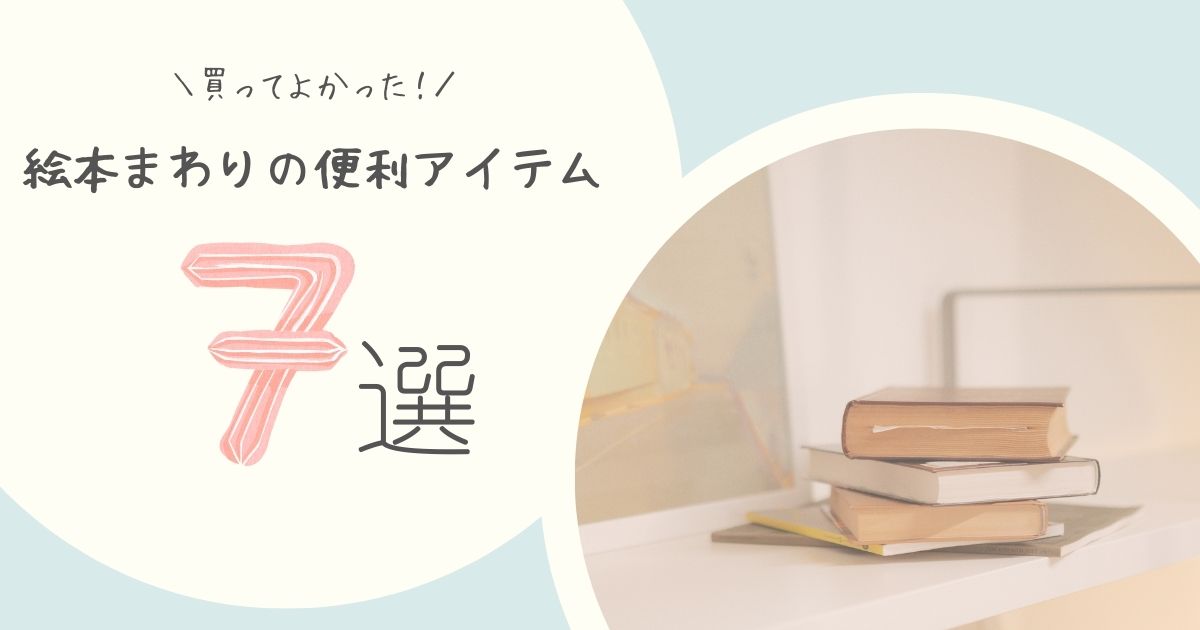絵本の読み聞かせって、子どもとの大切な時間ですよね。
お気に入りの絵本を読みながら、笑ったり、真剣に聞き入ったりーーそんなひとときは、育児の中でもほっとできる瞬間だったりします。
でも、毎日続けていると「すぐ飽きちゃう」「絵本が増えて片付かない」「寝かしつけの雰囲気が整わない」なんて、小さな困りごとも出てきませんか?
実は我が家でもそんな悩みがあって、いろいろ試してみた中で「これは便利!」と感じたアイテムがいくつかあります。
今回は、育児グッズと一緒に揃えてよかった【絵本まわりの便利アイテム】を7つご紹介します。
どれも毎日の絵本タイムをもっと快適に、そして楽しくしてくれたものばかりです。
1.表紙が見える絵本ラック
「せっかく絵本を買っても、子どもが全然読まない…」
そんな悩み、ありませんか?
我が家でも最初は、絵本を普通の棚に並べていたのですが、背表紙しか見えないと子どもが選んでくれず…。
そこで取り入れてみたのが、「表紙が見える絵本ラック」です。
このタイプは、まるで図書館の“面出し”のように、絵本の表紙を見せて収納できるのが特徴。
子どもがパッと見て中身を思い出しやすく、自分から「これ読む!」と持ってきてくれるようになりました。
特に0~3歳ごろは、「絵」で絵本を選ぶことが多いので、表紙が見えるかどうかはかなり重要なポイント。
1歳の下の子も、まだタイトルが読めないながら、好きな絵柄の絵本を繰り返し選んでいます。
見た目もスッキリしていて、リビングや子ども部屋の一角に置いてもごちゃつかず、“絵本コーナー”としての空間づくりにもぴったり。
最近では、おしゃれな木製タイプや、コンパクトで省スペースな布製ラック、回転式などもあるので、インテリアや置き場所に合わせて選べるのもうれしいポイントです。
💛我が家で使ってよかったポイント
・表紙が見えることで子どもが選びやすい
・「片づけ」も遊びの一部になりやすい
・リビングに置いてもなじむナチュラルデザイン
🔍選び方のヒント
・安全性重視:角が丸くて倒れにくいもの
・収納力:絵本が20冊以上入るかどうか
・素材と見た目:木製(ナチュラル感)or 布製(軽くて移動も◎)
💡おすすめアイテム例
・IKEA「FLISAT 絵本ラック」
・LOWYA「木製おもちゃ・絵本収納ラック」
・山善「絵本ラック」 など
2.ナイトライト・間接照明(寝かしつけにもぴったり)
寝る前の絵本タイム、みなさんはどんな明かりの中で読んでいますか?
我が家では以前、天井の照明のまま読み聞かせをしていたのですが、明るすぎてなかなか寝るモードにならず…。
そこで取り入れてみたのが、「ナイトライト」や間接照明でした。
やわらかい明かりに切り替えたことで、部屋の雰囲気がぐっと落ち着き、子どもも自然とリラックスした表情に。
「絵本を読んだら、だんだん眠くなる」流れがスムーズになり、寝かしつけの時間が短くなったのはうれしい変化でした。
さらに、ライトのデザインによっては子どもが「これつけるー!」と自分でスイッチを入れたがったり、「このライトをつけたら絵本の時間」と習慣化にも◎。
タイマー付きや調光機能のあるライトなら、そのまま寝落ちしても安心です。
💛我が家で使ってよかったポイント
・光を落とすだけで、寝かしつけの“スイッチ”になる
・寝室の空気が落ち着き、ママパパの気持ちにもゆとりが
・子どもが安心して眠りやすくなる
🔍選び方のヒント
・調光・タイマー付き:読み聞かせ後、そのまま寝ても安心
・充電式or電池式:コンセントが届かない場所でも使える
・デザイン性:インテリアになじむ、おしゃれなものを
💡おすすめアイテム例
・【BRUNO】LEDランタン(やわらかな色味が人気)
・【無印良品】充電式LEDナイトライト
・【BALMUDA】The Lantern(インテリア性◎)
・【Amazon】タッチ式ナイトライト(動物・ミッフィーなど子ども向けも)
「夜の絵本時間が楽しみになった」「寝室の空気が変わった」と感じたアイテムのひとつ。
毎日忙しい中でも、心を落ち着ける“照明の力”をぜひ取り入れてみてくださいね。
3.持ち運びできる絵本ボックス
「今日の絵本は寝室に持っていこう」
「今日はリビングでも読んでって言われるし…」
そんなふうに、読み聞かせする場所が日によって変わること、ありますよね。
我が家ではリビング→寝室→車の中と、絵本をあちこち運ぶ機会が多くなり、気付けば“絵本があちこちに点在”…。
そこで導入したのが、「持ち運びできる絵本ボックス」です。
読んだあとすぐ片づけられる、収納にもなる、とても気軽に移動できるーーそんな便利さがとても重宝しています。
特にお気に入りの絵本や、毎日読む定番を数冊まとめて入れておけば、「今日はどこで読む?」と子どもと一緒に考えるのも楽しい習慣に。
帰省やお出かけのときにも、そのまま持っていけて便利です。
💛我が家で使ってよかったポイント
・リビングでも寝室でも、読みたい場所に絵本を移動できる
・「今読む本」だけをまとめておけて、迷いにくい
・お片付け習慣のきっかけにも◎
🔍選び方のヒント
・軽くて安全な素材(布・プラスチックなど)
・持ち手付きで持ち運びやすいもの
・折りたたみ式なら使わないときも省スペース
💡おすすめアイテム例
・【IKEA】KNAGGLIG木箱(キャスターつけてDIYも◎)
・【DAISO/Seria】布製ボックス(低価格で複数使いも)
・【3COINS】収納バスケット
・【楽天・Amazon】キャスター付き絵本ワゴンなども人気!
ちょっとした移動がラクになるだけで、絵本タイムのストレスが減るのはもちろん、子どもにとっても“お気に入りを自分で運ぶ”という楽しさがあります。
読んだらここに戻す、という収納習慣にもつながる優秀アイテムです!
4.絵本の整理に便利なブックエンド
「絵本がラックの中でバタン!と倒れてぐちゃぐちゃ…」
「読んだあとに戻したはずなのに、いつの間にか片付いてない…」
そんなふうに、絵本が整って並ばないストレス、地味に積もっていませんか?
我が家でも、子どもが絵本を出し入れするたびに、他の絵本が一緒にドサッと倒れてしまい、プチイライラの連続でした。
そこで試してみたのが、「ブックエンド」。
シンプルですが、倒れ防止や整理整頓にとっても効果的なんです!
特に、絵本ラックの端っこに設置したり、ジャンル別や兄弟別に仕切って使うと、本が倒れにくくなるうえに「自分の本はここ」と子どもが意識しやすくなりました。
お気に入りのキャラクターのものを選んだことで、子どもも「ここに戻すよ~」と楽しく片づけてくれるようになりました。
💛我が家で使ってよかったポイント
・絵本が倒れなくなってストレス激減!
・仕切りの役割も果たすから整理整頓しやすい
・キャラものを選ぶと子どもも喜んで使う
🔍選び方のヒント
・重さ・安定感があるもの:軽すぎると逆にズレてしまうことも
・角が丸い・安全な素材:怪我防止にも注目
・好きなキャラクターやデザイン性:自分のスペース感が出しやすい
💡おすすめアイテム例
・【アンパンマン】や【ミッフィー】のキャラブックエンド
・【無印良品】スチールブックエンド(シンプル&しっかり)
・【100均】セリア・キャンドゥの木製タイプもコスパ◎
・【ニトリ】1冊でも倒れないブックスタンド
我が家では、1歳の弟用と3歳の姉用でエリアを分けてブックエンドを設置。
「私の絵本はここ」と意識するようになったことで、自然とお片付けもスムーズになりました。
ちょっとした工夫で絵本ラックがグンと快適になる、おすすめアイテムです!
5.お名前スタンプで絵本の管理もスムーズに
「絵本って、おうちだけじゃなく外でも使うことがあるんだなぁ」
ーーこれは、我が家が保育園に通い始めた頃に実感したことです。
連絡帳に「明日はお気に入りの絵本を1冊持ってきてください」と書いてあったり、児童館や図書館に持参したり。
ふと気づくと、絵本にも名前を書かないといけない場面って意外とあるんですよね。
そんな時に便利なのが、「お名前スタンプ」。
シールも便利ですが、スタンプもポンッと押すだけでOK!
紙質を選べばきれいに押せるし、シールのように剥がれる心配もなし!
何冊にも名前を使い分けたい時や、兄妹それぞれの名前を使い分けたい時にとても便利です。
💛我が家で使ってよかったポイント
・シールより早くて、見た目もスッキリ!
・水に強いインクなら長く使える
・布やおもちゃにも使えて、兄弟分まとめて準備できる
🔍選び方のヒント
・ひらがな&ローマ字のセットタイプが便利(保育園の園グッズにも)
・インク付きor別売りタイプかチェック
・耐水性インクなら洗濯やにじみも安心
💡おすすめアイテム例
・【シャチハタ】おなまえスタンプ(収納ケース付きで超便利)
・【おなまえ~る】イラスト入りスタンプセット(兄弟使いにも◎)
・【楽天・Amazon】名前スタンプ+スタンプ台+補充インクの3点セットなどお得感あり
ちなみに、うちでは上の子のスタンプを下の子にも…と思っていましたが、スタンプを見るたびに「これは私のだよね!」と子どもがうれしそうにするので、それぞれに用意してよかったなと思っています。
見た目はちょっと地味なグッズですが、育児中に「あると確実に助かる」便利アイテムのひとつです!
6.絵本カバーでお気に入りを長く使える
お気に入りの絵本って、つい何度も何度も読んじゃいますよね。
でもそのぶん、汚れたり・破れたり・角が折れたりとだんだんボロボロになってしまうことも…。
特に0~3歳ごろの子どもは、読むというより「めくる」「かじる」「投げる」なんてこともよくあるので、絵本の痛みは避けられません。
そんなときに役立つのが、「絵本カバー」です。
ビニールタイプや布タイプがあり、1冊ずつ大切に保護できるので、絵本が長持ち。
我が家では、お気に入りすぎて何度も読んでいる1冊にだけカバーをかけて使っています。
さらに、お出かけ用の持ち歩きにも便利で、リュックにポンと入れても安心感◎
1冊用のカバーならコンパクトに使えて、持ち運び絵本としても重宝します。
💛我が家で使ってよかったポイント
・お気に入りの絵本が破れにくくなった!
・汚れを気にせず持ち運べて、お出かけにも便利
・「これだけは守りたい」絵本にぴったりの安心感
🔍選び方のヒント
・透明ビニールタイプ:絵本の表紙が見えて管理しやすい
・布製カバー:柔らかくてかわいいデザインも多い
・サイズ確認は必須!特にしかけ絵本や大型絵本は注意
💡おすすめアイテム例
・【100均(DAISO/Seria)】透明ブックカバー(サイズ展開豊富)
・【ハンドメイド作家さん】布製ブックカバー(minnneやCreemaでも人気)
・【楽天・Amazon】フリーサイズタイプやマジックテープ式の簡単カバー
子どもが寝る前に「これ、読んで」と持ってくるボロボロの絵本を見るたびに、「この1冊、大事にしてあげたいな」と思うんです。
そんな気持ちに寄り添ってくれる絵本カバー。
絵本を“消耗品”にしないために、大人からできるちょっとしたケアアイテムです。
7.読み聞かせスペースに!クッション&ラグ
毎日読み聞かせしていて感じるのが、「読む場所」が決まっていると、子どもが集中しやすいということ。
ソファだったり、ベッドの上だったり、リビングの床だったり…
いろいろ試してみた結果、我が家では「このラグの上で読む」と決めたことで、絵本タイムの習慣がぐんとスムーズになりました。
そこにお気に入りのクッションや小さな座布団を置くと、子どもはちょこんと座って、自然と“読み聞かせモード”に。
「このクッション持ってきたら読む時間だよね!」なんて、合図代わりにもなります。
また、大人にとっても、床に座って読むのって意外と疲れるもの。
厚みのあるラグやビーズクッションがあるだけで、読み聞かせの時間がグッと心地よくなりますよ。
💛我が家で使ってよかったポイント
・「読む場所」ができて子どもが落ち着きやすい
・ママパパの腰や足もラクになって、長く読んであげられる
・雰囲気づくりにもなって、絵本タイムがもっと特別に
🔍選び方のヒント
・滑りにくい・洗えるラグ:食べこぼし対策や衛生面も◎
・低反発orビーズクッション:大人にも子どもにも心地いい
・インテリアになじむ色・素材:ナチュラル系が人気
💡おすすめアイテム例
・【ニトリ】ウレタン入りラグマット(滑り止め&洗濯OK)
・【しまむら】プチプラで子ども用ラグが揃う
・【無印良品】体にフィットするソファ(兄弟の取り合い注意!)
我が家では、小さな動物柄のマットを「絵本ゾーン」として敷いたら、自然とその上に座るようになって、「ここで読む」と子どもの中にリズムができたのを感じました。
お気に入りの1冊がもっと特別に感じられるような、そんな小さな“絵本の居場所”を、ぜひつくってみてくださいね。
🧺まとめ|ちょっとの工夫で、絵本タイムがもっと快適に
絵本の読み聞かせは、子どもとの大切なコミュニケーションのひととき。
でも、「続けること」「快適に過ごすこと」って、実はちょっと工夫やアイテムの力でグッと楽になるものなんですよね。
今回ご紹介した便利アイテムは、どれも実際に使って「これよかった!」と感じたものばかり。
片づけやすくなったり、集中しやすくなったり、子どもが自分から絵本に手を伸ばしたり…。
ほんの少しの変化でも、毎日の育児がぐっと心地よくなります。
「絵本タイムがうまくいかないな」と感じた時は、環境やツールを見直してみるのもひとつの方法です。
ぜひ、気になるアイテムから試してみてくださいね。
📚合わせて読みたい関連記事
寝かしつけ前の読み聞かせにぴったりな絵本を、年齢別に紹介しています。
子どもが夢中になる!遊びながら楽しめるしかけ絵本を、年齢別にご紹介しています。
📖子どもが絵本を好きになるには?0~3歳の“絵本習慣”の始め方
読み聞かせが習慣になるちょっとしたコツや、親子で楽しむ工夫をお届け。