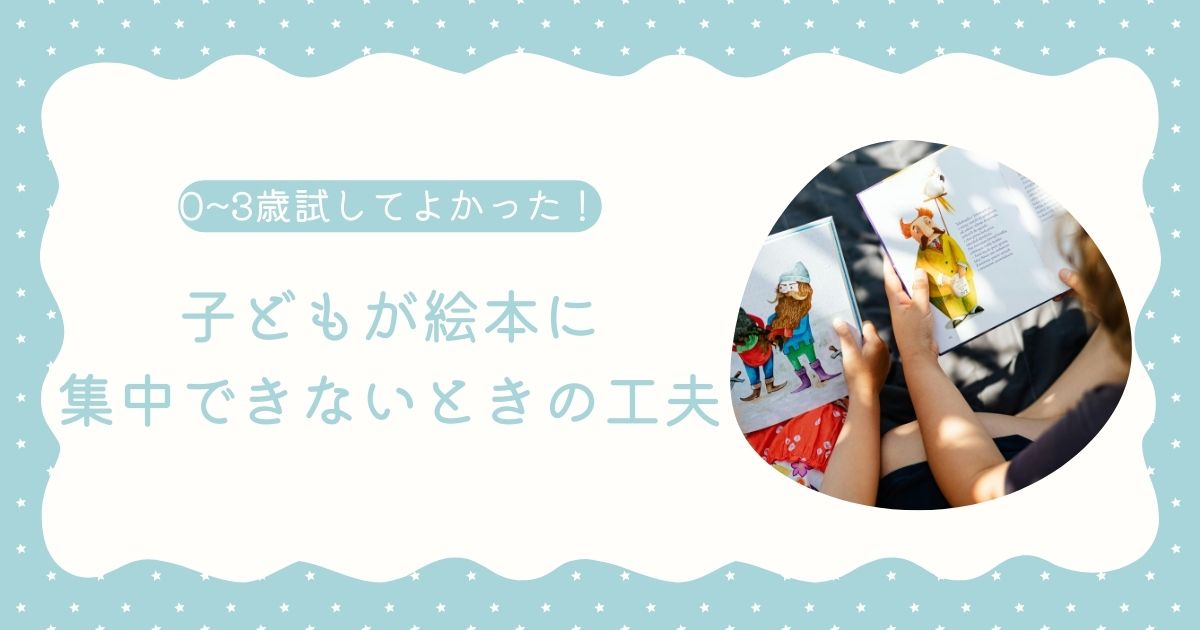「せっかく絵本を読もうとしたのに、全然集中してくれない…」
「すぐに立ち上がっちゃって、最後まで読めたことがない…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
我が家でも、上の子のときは特にそうでした。
絵本タイム=バタバタな時間…そんな日が何度もあったんです。
でも、いくつかの小さな工夫を取り入れてみたら、「もう1回読んで!」と自分から絵本を持ってくるようになったんです。
子どもの集中力は年齢や性格によってもまちまち。
無理に読ませようとせず、「楽しい時間」にしてあげることがいちばん大切だと感じています。
今回は、我が家でも実際に試してよかった「子どもが絵本に集中できないときの工夫5つ」を、具体例とともにご紹介します。
「うちの子にも合いそう!」と思えるヒントが見つかりますように。
なぜ集中できないの?子どもが絵本に飽きる理由とは
「ちゃんと座って聞いてくれないのは、うちの子だけ…?」
そんなふうに感じてしまうこと、ありますよね。
でも、0~3歳の子どもたちは、もともと集中力が続かないのが当たり前なんです。
まずは、「集中できないのは自然なこと」と知るだけでも、少し心が軽くなるかもしれません。
ここでは、子どもが絵本に飽きてしまう理由を3つに分けて紹介します。
①発達段階による集中力の差
0~3歳の子どもは、数分でもじっとしているのが難しい時期。
特に1~2歳のうちは、言葉の理解もまだ発展途中です。
「ページをめくるのが楽しい」
「絵が動くと思って触ってみたい」
そんな気持ちの方が強くて、物語をじっくり聞く…というのはまだ先の話。
月齢や個性によって、できることに差があるのは当然です。
②興味や好みに合っていない絵本かも?
大人が「これはいい本!」と思っても、子どもにとっては興味のないテーマだったり、絵が怖かったりすることも。
例えば…
- 動物が好きな子には、動物が出てくる絵本がハマりやすい
- シンプルなくり返しが好きな子には、ストーリーよりリズムが大切
「どんな絵本なら夢中になるか」を探ることも大切なステップです。
③環境やタイミングの問題も
- お腹が空いている
- 遊びに夢中なときに読もうとしている
- テレビやおもちゃなど、他の誘惑が近くにある
こうした状況では、どうしても絵本に気が向きません。
集中できる「時間」や「場所」を整えるだけで、ぐっと変わることもあります。
まとめ
「読まない=ダメなこと」ではなくて、今は絵本よりも心が動くものがあるというだけのこと。
子どものペースに合わせながら、少しずつ絵本の楽しさに触れられるようにしていきましょう。
子どもが絵本に集中できないときの工夫5つ
次に、子どもが絵本に集中できないときの工夫を5つ紹介していきます。
①時間は3分でOK!短く切って読む
「絵本って、最後まで読み切らなきゃいけないもの」
そう思っていませんか?
でも、実は全部読まなくても大丈夫なんです。
0~3歳の子どもにとって、10分座って話を聞くのはとても大変なこと。
まだ、「集中力を持続する力」が発達途中なので、途中で立ち上がったり、ページをめくったりするのも自然な姿です。
だからこそ、最初は3分だけ、1ページだけでもOk。
無理に最後まで読もうとせず、「ちょっと読んでみる」くらいの気持ちで十分なんです。
例えば…
- 朝の支度前に1ページだけ
- 寝る前に「今日はこのページまでね」と区切る
- 子どもが興味を示したところだけ読む
こんな風に、短く・軽く・楽しく始めてみましょう。
大人にとっては「短すぎるかな?」と思っても、子どもにとってはその数分が、絵本の世界と出会う大切な入り口になります。
まずは、“集中できる”より、“楽しかった”が残るように。
気軽に始めてみてくださいね。
②読むタイミングを見直す
子どもが絵本に集中できないとき、“読むタイミング”が合っていないだけ…ということもよくあります。
例えばこんなタイミング、思い当たりませんか?
- 遊びに夢中にな時に「そろそろ絵本読むよ~」
- お腹が空いていてぐずっているとき
- 眠くてご機嫌ナナメな時間帯
これでは、どんなに魅力的な絵本でも子どもの心には入りません。
大人でも、疲れているときに長い話を聞くのはしんどいですよね。
我が家の場合は、「お風呂あがり」や「寝る前」が落ち着いていて◎でした。
特に寝る前の絵本タイムは、
- スキンシップがとれる
- 一日の終わりに気持ちを切り替えやすい
- 「絵本→ねんね」の流れが習慣になる
と、いいことづくし。
逆に、朝の忙しい時間帯や遊びに夢中なタイミングは避けるようにしています。
無理に読ませようとしないことが、楽しい時間をつくる近道かもしれません。
子どもにとって「今、絵本の気分かな?」と少し様子を観察してみるのも大切なポイント。
その子のリズムに合わせた“ベストタイミング”を見つけてみてくださいね。
③子どもの好みに合わせた絵本を選ぶ
「この絵本、口コミも高評価だし、きっと気に入るはず!」
そんな思いで選んだ絵本なのに、全然反応してくれなかった…
という経験、ありませんか?
実は、“良い絵本”と“その子に合う絵本”は違うこともあります。
大人にとっては「優しいお話」や「感動てきなストーリー」でも、子どもにとっては難しかったり、興味が持てなかったりする場合も、
そこでおすすめなのが、子どもの“今の好み”に合わせること。
例えば…
- 動物が好き→動物がたくさん登場する絵本
- 手を動かしたい→しかけ絵本や触れる絵本
- 「自分でやりたい」気持ちが強い→参加型の絵本(ボタンを押す・めくるなど)
選び方のポイントは、“何ページあるか”より“何にワクワクするか”。
子どもが目をキラッとさせた瞬間をヒントにしてみてください。
また、同じ絵本を何度も読みたがるのも、興味がある証拠。
飽きていないなら、“くり返し読む”のも立派な集中タイムなんです。
子どもの「好き」や「ハマっているもの」に寄り添えば、自然と絵本の世界にも入りやすくなりますよ。
④一緒に声を出したり動きをつけたり
絵本のう読み聞かせ=静かに読むもの、と思っていませんか?
でも実は、声や体を使って一緒に楽しむことで、子どもの集中力がグッと高まることがあります。
例えば…
- 「わんわんがきたよー!」と声を大きくしてみる
- 「ぴょーん!」の場面でジャンプしてみる
- 「もぐもぐ」「ぱくっ」などのオノマトペを一緒に言ってみる
- ページをめくるタイミングで「せーの」と声をかける
こんなふうに、絵本の世界に親子で“入り込む”工夫をすると、自然と夢中になってくれます。
特におすすめなのが、子どもが真似しやすい“繰り返し言葉”や“動作”がある絵本。
例えば…
- 『だるまさんが』シリーズ→ゆらゆら・どてっ の動きが楽しい
- 『ぴょーん!』→一緒にジャンプで大盛り上がり
- 『もこもこもこ』→不思議な音と動きに引き込まれる
「読む」というよりは、「一緒に遊ぶ」くらいの気持ちでOK。
大人がちょっとは恥ずかしさを手放すと、子どももぐっと楽しめるようになります。
子どもは、言葉だけよりも五感を使った体験の方が記憶に残りやすいもの。
「声を出す・体を動かす・笑う」この体験が、絵本への興味を育ててくれますよ。
⑤無理に読ませようとしない
「最後まで読まなきゃ」
「ちゃんと座って聞いてほしい」
そう思うのは、親として自然な気持ちですよね。
でも、絵本って“読まなきゃ”じゃなくて“楽しむもの”。
子どもが途中でどこかに行ってしまったり、ページを飛ばして読んでほしがったりするのは、興味がないのではなく、「自分なりの楽しみ方をしている」だけかもしれません。
ときには…
- ページをめくるだけでもOK
- 表紙を見ているだけでもOK
- 途中でおもちゃに気を取られてもOK
そんなふうに、絵本とふれる“ゆるさ”を大切にしてみてください。
我が家でも、「最後まで読めた!」なんて日は、最初のうちはほとんどありませんでした。
でも、それでも続けているうちに、少しづつ「読んで」「もう一回」と言ってくれるようになりました。
大事なのは、「読んでもらうのが楽しい」「絵本が好き」という気持ちを育てていくこと。
その土台ができれば、自然と集中力もついていきます。
焦らず、比べず、子どものペースに寄り添っていくことが、一番の近道かもしれません。
それでも集中できないときは?
ここまでいろいろ工夫しても、「それでも全然集中してくれない…」
そんな日もありますよね。
でも大丈夫。
絵本との関わり方に“正解”はありません。
子どもによって、絵本に興味を持つタイミングやきっかけはバラバラ。
今はまだその時期じゃないだけかもしれません。
そんなとき、絵本以外の“楽しいこと”からスタートしてもOKです。
例えば…
- 絵本の代わりに、手遊びやお歌でスキンシップ
- 親子の会話を増やして、ことばの楽しさにふれる
- 絵本の代わりに、写真やカタログなど「見るもの」にふれる
- 絵本棚の前にお気に入りのおもちゃをおいて、「ついでに絵本を見る」環境にする
などなど・
絵本にこだわらず、「ことばに親しむ経験」を日常にゆるやかに取り入れるだけでも、十分です。
また、子どもが絵本に集中しにくいときは、
- 絵本の対象年齢を見直す
- 文字数の少ない絵本や、色彩がはっきりした絵本に変えてみる
といった工夫もおすすめです。
なにより大切なのは、ママ・パパが疲れてしまわないこと。
「今日は無理そうだな」と思ったら、潔くお休みするのも大事な選択です。
絵本は、いつでも、何度でも。始め直せます。
📚集中しやすかった!我が家のおすすめ絵本3選
ここでは、実際に我が家で集中して楽しめた絵本を3冊ご紹介します。
動きやリズムがあって、0~3歳の子どもでも夢中になりやすいものを選びました。
①『やさいさん』 tupera tupera
しかけ絵本の人気作。
「やさいさん やさいさん だあれ?」と、土の中から野菜が出てくる楽しい仕掛けに、子どもが大笑い!
✅繰り返しのフレーズでリズムが心地よい
✅手でめくる楽しさがあるので、自然と集中できる
✅野菜に興味を持つきっかけにも◎
▶
👉「しかけ絵本が好きなお子さんには、こちらの記事もおすすめです」
②『だるまさんが』 かがくいひろし
「だ・る・ま・さ・ん・が…」のリズムで。ページをめくるたびにクスッと笑える絵本。
動きのある展開と、わかりやすい言葉で0歳から大人気!
✅声に出して読むのが楽しい
✅同じ展開のくり返しで安心感あり
✅読むたびに笑顔になれる1冊
▶
③『もこ もこもこ』 谷川俊太郎、元永定正
不思議な音と形の世界が広がる絵本。
「もこ」「にょき」「ぱくっ」といった擬音語がたまらなく面白くて、子どもがじーっと見つめることも。
✅文字が少なくてテンポよく読める
✅想像力を刺激するビジュアル
✅読み方次第で何通りもの楽しみ方ができる
▶
まとめ
いずれも短め&リズムが心地よいので、集中力が続かない子にもぴったり。
まずは「楽しい!」という気持ちを育てる1冊として、ぜひ取り入れてみてくださいね。
まとめ:絵本の時間は「完璧」じゃなくていい
子どもが絵本に集中してくれないと、
「ちゃんと読まなきゃ…」
「他の子はもっと集中してるのに…」
と、不安になることもありますよね。
でも、絵本の時間に“正解”はありません。
たとえ最後まで読めなくても、途中で飽きてしまっても。
それでも親子で絵本を開いたという時間は、確かに子どもの心に残っています。
今日が2分でも、明日は3分読めるかもしれません。
子どもは、少しずつ少しずつ、“絵本って楽しい”を育てていくものです。
完璧を目指さなくていいんです。
大切なのは、親子で絵本を「楽しもう」とする気持ち。
焦らず、比べず、その子のペースに合わせた絵本の時間を、これからも一緒に楽しんでいけたらいいですね。
▼よければこちらの記事もどうぞ